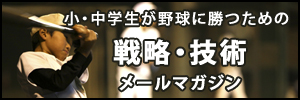球の出し入れという専門用語。
コントロールの良いピッチャーの特徴で、特に球威がないピッチャーに見られるこの技。
簡単には、出し入れとはストライクをストライクコースへ、
ボール球をボールコースへ意図して投げることを言う。
もう少し詳しく言うと、意図したところでストライクをとり、同じ軌道から変化させて
ボールにさせて空振りをとるとか、内野ゴロを打たせるとか、見逃されたとしても
次のボールに生かすとか。
その逆にボールからストライクに入れてくるとか。
フロントドアとかバックドアとか。
球威がないピッチャーに見られる理由は、ストライクコースだけに投げていては打たれてしまうので、
ボール球を使わざるを得ないからだ。
球威だけでも抑えられるピッチャーはどんどんストライクコースに投げて行き、
空振りをとったり、フライを打たせたり、で打ち取ることができるので、
ボール球が不要だ。
江川は典型的な球威のあるピッチャーで、いわゆるパワーピッチャーだった。
球種はストレートとカーブだけ。
それでも浮き上がるといわれた真っ直ぐをストライクコースへどんどん投げ込むわけだ。
バッターは、それを空振りしてしまう。
ボール球がいらないということになる。
当時、落合は「真っ直ぐとわかっていて空振りするのは江川だけ」と発言していた。
だから江川は、打者のバットがクルクル回る大きく鋭いフォークボールを評価しなかった。
「すごい球と言っても見逃せばボールなんだよね」
相手が振ってくれないと勝ちとならないボールは、本当にすごい球とはならないことを示唆した。
江川のような特別な球があれば、ストライクコースで勝負できる時代があった。
技術が発達し、情報研究が盛んな今の野球で、ストライクコースだけで勝負するのは不可能ではある。
というより、ストライク以外を駆使して勝負するところに野球の面白さがある。
ボール球を使う理由は、ストライクだけで勝負しても打たれることと、
ボール球は打ってもヒットにならないからだ。
ならば、バッターはボール球を打たなければいいはずなのに手を出てしまう。
それが出し入れの技術ということ。
例えば、初球、外角へストライクが来た。
バッターは内角を狙っていたから手を出さない。
しかし、その球筋は1球見たことで頭に入る。
そこへ同じコースへ2球目が投じられた。
先ほどの球が頭にあるので今度は打てると判断する。
そしてバットを出していくと、そこからボール球に変化する球だった。
これによりボール球に空振りや内野ゴロとなっていく。
遠くにあるものの大きさや形の差はわかりづらいもの。
星の大きさは距離の違いでその差はわからない。
距離がはるかに違うので、大きさが全然ちがうものが同じ大きさに見えてしまうのだ。
バッターにとってピッチャーの近くにある球、つまりバッターから遠くにある球は、
どのくらいのスピードで、どんな球種で向かってきているのか判断しづらい。
わかるのは自分の近くに来た時に、やっと「はえ~。」とか「あっ曲がった。」となるので、
この時は時すでに遅し、となるか、手が思わず出てしまっている、という状態になる。
こうして、ボール球にも手を出していくのだ。
同じ軌道で同じに見えるフォームで投げると効果が出る。
同じ軌道から内、外、下へと変化させるのだ。
出し入れできるピッチャーはボールをボールとして意図して投げる。
ストライクを投げようとして思い切り投げたのだけれど、ボールになってしまい、
でも球の威力で空振りを取ることができた、というのは出し入れではない。
ファールにさせようと投げ込む。
ボール球をそこへ狙ってわざと投げて、バッターがどんな反応するか、
あーそうなのね。という情報を得て、
じゃあここに投げれば振るでしょ、
やっぱりね、
ということができるピッチャーが出し入れの出来るピッチャー。
また、相手が打ちたいところにワザと投げてやる。
打ち気満々のバッターはよしっと振りに来て、そこからその軌道でボールにして振らせる、
打ち取る、という術も出し入れのできるピッチャーの特徴だ。
出し入れというのはピッチャーの高度な技術だが、早くから身に着けなければいけないものではない。
球威を磨くというのは若い頃の方が可能性が高いが、出し入れという技術は、
球威に限界を感じてからや、体の成長が止まってからでもでも遅くはない。
打者が打ちにくい、あるいは嫌がる、あるいは手強いと思うピッチャーは、
やはり球威のあるピッチャーだから。