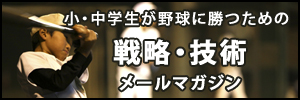数年間の厄災により甲子園大会が中止になるという、今生きている者にとっては経験のない出来事に、
関係者、出場チームからは無念の声が漏れ、選手には同情する声が多かった。
出場予定だったチームには何らかの救済措置を、と声が上がった。
世の中がそういう心情になる大きな理由のひとつに甲子園出場は青春を賭して
一生懸命やっている子供たちの夢であり、その子供たちは無垢な気持ちで没頭して取り組んでいる。
その結果、勝ち取った栄光だから、ということがある。
そして、最後の夏のたった一度の敗戦に崩れ落ちる高校生達を見てきているので、
これらの高校生たちに同情するのだ。
たとえ、強豪校で野球に打ち込んできたチームでなくとも、限られた時間と設備の中で、
野球を生活の一番手に位置づけ、情熱を燃やしてきたが、夏の一試合で負けてしまえば、終わりを突き付けられる。
そして、その瞬間、違う生活を送ることを余儀なくされ、その気持ちの切り替えができず、
虚脱感が襲いながら夏休みを送ることになる。
野球に専心しながら負け、涙にくれる姿にはレベルや実力など関係なく、お疲れ様、
よくがんばったね、と言いたくなるものだ。
高校野球は、プロから注目されるほどの実力者も高校生活の青春の一ページでやっている野球好きも
同じ限られた時間の中で活動するという制約がある。
プロへ行くことが既定路線であり、高校野球は通過点のはずの清宮も
夏に敗れたときのコメントは
「3年生ともうできない。悔しいです。自分たちを背中で引っ張ってくれた人たち。金子さん、副キャプテンの吉村さんは泣かずにすがすがしい顔をしてて、自分たちは頼り切っていたんだなと。(甲子園に)連れて行きたかった」
さらに
「西東京を勝ち抜くのが一番難しい。今年、改めて難しさを実感させられた。甲子園は本当に遠いところ。この経験、この悔しさを共有して、日々練習に取り組んでいきたい」
この時の涙というのは、まずなにより目の前の勝負に敗れた悔しさだ。
それからそれぞれにたてた目標に届かなかった悔しさがつのる。
そして、同じ高校生として同じ目標に同じ時間を共有した者同士が別れを告げられる寂しさ。
自分より実力が劣る選手であっても一緒に濃い時間を過ごした仲間との別れはとても寂しい。
野球の技術の向上だけを考えれば、
清宮が高校野球のレベルで時間を使っているのはもったいなかったと言える。
しかし、そんな考えは毛頭浮かばないかのように涙に暮れることで、野球どうのこうのより、
濃い時間をすごした人間のつながりを知ることになり、
人生の肥やしとして次の勝負への意欲につながっていく。
人間のつながりが、野球という遊びを凌駕して胸にしみるから涙に暮れるのだろう。
人間としての成長に野球というツールを利用していることになる。
そしてその人間としての成長が野球の技術向上にも生きてくる。
今まで一所懸命やってきたのにいきなり終わりを告げられるその人生最上級の虚脱感、脱力感は、
その選手のそれからの糧になる。
たった2年数か月の出来事なのに、この濃い時間を過ごした経験のある人とは
世代など関係なく、話題は尽きることなく一生語り合える。
それだけ、濃い時間であり、人生に必ず影響を与える。
財産となる。
高校生という枠組みにこの仕組みをあてはめたことが、予期せず、大きく地平を開いた。
野球を志した先輩の所業を継いできた100年間の選手たちのおかげで大きな文化に発展した。
高校野球は、高校生活という限られた二度と戻らない時間の中で行われること。
味方も相手も同世代の人間で行われること。
考えも体も未熟だが、多くの時間をそこへつぎこむこと。
大人の感覚も持ち合わせてきて、とても感受性が高く、吸収力のある時期に入魂すること。
このような境遇は人生の中でこの時しかない。
故に特別な連帯感が生まれるものなのだ。
今、プロで活躍する選手の中にも高校野球のたった一試合のためにつぶれてもいいと賭ける選手が多くいた。
冷静、沈着な振る舞いが印象的な大谷すら甲子園で負けたときは号泣だった。
大谷が背中を追って選んだ花巻東の激情家の先輩・菊池はいわずもがな、
ここで野球人生が終わってもいいという感情さえ湧き起ってしまった。
前田は、大阪大会で温存敗退してしまい、立ち上がれないほど泣き崩れた。
ヤンチャなイメージがある森も。
クールなイメージがあるダルビッシュも。
王は、プロ野球はもういいが、高校野球は、もう一度やってみたい、と言っていた。
日本を代表する野球選手たちが、二度と来ないこの瞬間に涙してきた。