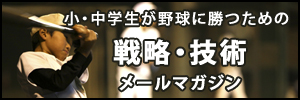育成という仕組みにより、必ずしも野球一貫してきたわけではない人がプロになっている。
高校時代、バレー部だった松田という例もある。
高校在学中に身長が伸びると、中学まで続けていた野球をもう一度、大学で取り組むことになる。
大学に入学した頃は175センチで62㌔程度、初めての硬式野球となった。
その細身の体で、真っ直ぐは高校生の中に入っても遅い部類に入る程度だったものが、
1年の秋までに、急成長を見せ、140㌔を計測するまでになったそうだ。
名古屋大学という国立の一流大学なのだから相当、勉強も頑張ったはず。
名大は3部リーグであり、これまでもプロ野球選手はいない。
高校時代に野球から離れ、学力で一流大学へ進み、そこから野球で立身するなどというストーリーは
おそらく、前人未到の出来事だろう。
松田の場合は特異な例ではあるが、ジャパニーズドリームの1種だ。
育成枠はその名の通り、こういう選手が出てくる可能性がある環境なので、
そこから一軍で活躍すると這い上がってきたように紹介されることが多いが、
例えば、高卒で育成ならそう雑草でもない。
なぜなら、高校時代はドラフトにかからなかったり、あるいは無名の選手でも
大学4年間で成長したことで上位指名されることはザラにあるからだ。
上原などは典型だ。
育成期間を大学に進んで成長した期間と捉えれば、同じことだ。
高校生の青田買いにドラフト指名するにはプロも慎重になる。
将来どうなるかわからない選手にお金と居場所をつくるのは、博打になるから。
育成といえど、高卒でプロから誘われたということは、その時点で才能を認められており、
充分な野球エリートだ。
大学4年間と育成3年では、そう変わらないのに、印象、評価、通称は
エリートと雑草という、全く逆なものになりがち。
高卒育成出身の千賀は松田とは比べ物にならないくらいエリートの方に近い
立場だったということになる。
若いうちは、伸び盛りだからアマチュア時代の実績や実力を凌駕して
想像以上に化ける可能性が多くある。
そもそも、育成という制度が、そういう選手が出るからつくられた仕組みだ。
若い選手に、給料は安く、一軍の試合には出られないけれど、3年間のチャンスをあげるから
夢を追いかけてみなさいということで、門戸を広げた。
選手の夢と球団の希望が合致した、大成功の仕組みといえるだろう。
3年間のチャンスで結果が出なければ、夢を追った選手もあきらめがつき、
次の人生へ向かいやすいと思われる。