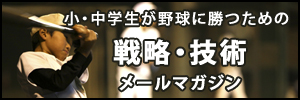変化球についての考察を振り返る金曜連載7回目。
2023-8-18 変化球は握り(スプリット)、軌道(スライダー)、効果(チェンジアップ)にわかれる
2023-9-1 ツーシームとシュートの違いは そしてシンカー
2023-9-8 カットボールとスライダーの軌道 カーブは大きい曲線
2023-9-15 変化させない変化球チェンジアップ タイミングを外せばいい
2023-9-22 スライダーもツーシームもチェンジアップも全て下へと落ちる
カットボールはスライダーの小さい球、スプリットはフォークより速く、落ちが少ない、
ツーシームはシュートと一緒と言っていいが、シュートの中でも縫い目が二つ見えるように打者へ向かう球。
それぞれ打者への効果を変えた球があり、中にはどちらでもいいものもあるので
見ている方は判断つきにくい。
しかもピッチャー本人がスライダーを投げたつもりが意図した変化でなく、
少しだけ動くことでカットボールのような効果となり、内野ゴロなんてこともある。
こうなると、解説者としては自信をもって、「今のはカットボールです」と言うだろう。
それはそれでいい。
その球種を推測し、バッテリーの意図を知ることにより、勝負の駆け引きを読み、楽しむ。
こういう時、良く「カットボールですかね、スライダー系の球です」とか言う。
スライダーという昔からある球と同じ系統がカットボールだから、”スライダー系”となる。
変化球には同じ系統の球に分類され、スライダー系、シュート系、フォーク系、チェンジアップ系などとなる。
逆にカット系と言ったり、ツーシーム系と言ったりすることもある。
変化が小さいのでちょっと動いて見えるな、と思うとこう表現するわけだ。
こうして表現が難しくなった変化球だが、ついに現れた表現が
実況が
「次はどのような球でしょうかね?」とか「バッテリーはどう攻めていきますか?」
といった質問に、
「バッテリーの意図としてはできればゴロを打たせたいですから、2球目のファールを見ていても、
最後は○○系で行くはずです」
などと言う。
この○○系がとんでもないのだ。
それは次回へつづける。